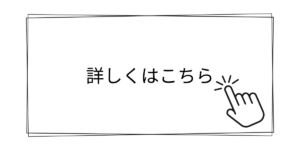「子ども部屋は2階」が常識?―暮らしの変化に寄り添う柔軟な間取りの考え方
2025.08.08
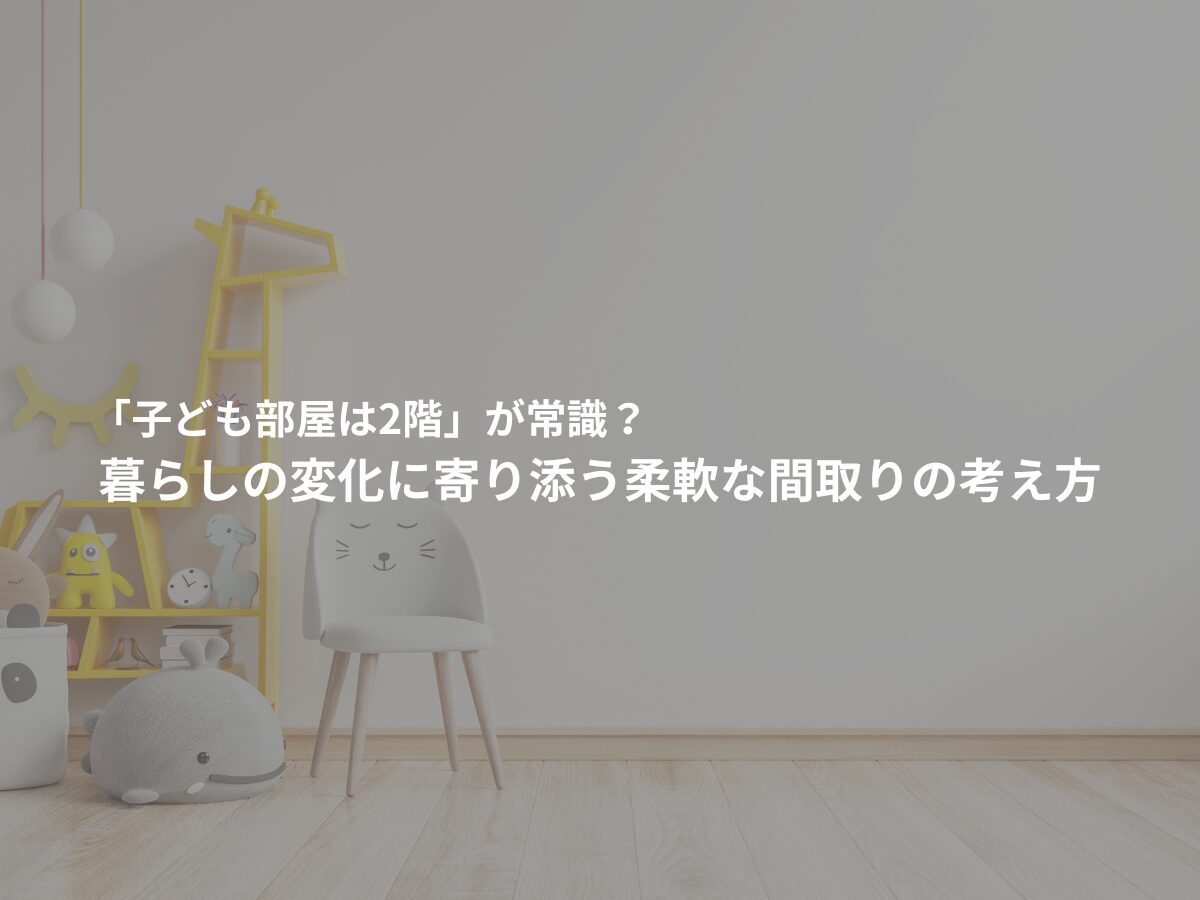
こんにちは。シンプルノート熱田/一宮スタジオの堀内です。
家を建てる―それは、多くの人にとって人生の中でも大きな決断ですよね。
そんな大切なタイミングで「2階建て」「子ども部屋は2階」という“当たり前”の考え方に、なんとなく従ってしまっていませんか?
ですが、家づくりにおいて本当に大切なのは、「家族のこれからの暮らし方」に柔軟に対応できること。
今回は、そんな視点から「子ども部屋=2階」という前提を少しだけ疑ってみたいと思います。
CONTENTS
ライフステージで考える、間取りの正解
家族の暮らしは、時間と共にどんどん変化していきます。
今回は、以下の4つのライフステージで「子ども部屋のあり方」について見ていきましょう。
1.子どもがまだ小さい頃
2.思春期を迎えた頃
3.子どもが巣立った後
4.夫婦が歳を重ねたとき
1.子どもが小さいうちは「2階の子ども部屋」がほぼ使われない
お子さんがまだ小さいうちは、「親と一緒にいる時間」がほとんど。
せっかく2階に子ども部屋を作っても、実際には使われず、おもちゃや絵本がリビングに溢れかえってしまう…なんてことも。
その度に片付けや掃除、階段の上り下りが増えて、親にとっては手間の多い暮らしに。
そこでおすすめなのが、1階に“子どもスペース”を設けるという発想。
目の届く範囲で子どもが安心して遊べて、片付けもしやすい。何より、生活動線がシンプルになります。
2. 思春期は「プライバシー」重視。2階が活きる期間
思春期に入ると、子どもはプライベートな時間を大切にするようになります。
友達との通話や勉強に集中したい時間。
そうなると、親と少し距離を置ける2階の子ども部屋は理想的に感じるかもしれません。
ただし、注意したいのは「この期間は案外短い」ということ。
中学生〜高校生の数年間だけのために、家全体の間取りを決めてしまうのはもったいないかもしれません。
3.巣立ったあとの「子ども部屋」はどうなる?
子どもが大学進学や就職、結婚で家を出ると、かつての子ども部屋は“空き部屋”になります。
このとき、部屋が2階にあると、活用方法が限られてしまうことも。
たとえば、趣味部屋や収納として使いたい場合、1階にあればもっと便利だった…と感じる方は少なくありません。
最初から「将来多用途に使える部屋」として1階に設けておけば、来客用の部屋や趣味のスペース、あるいは夫婦どちらかの書斎としても再利用できます。
4.自分たちの“老後”こそ、1階完結型が理想
家づくりで見落とされがちなのが、「将来自分たちが歳をとったとき」の暮らし。
体力が落ちて階段の上り下りがつらくなったり、膝や腰の不調が出てくる頃に、“毎日使う部屋が2階”というのはかなりの負担になります。
洗濯、食事、寝る場所―生活のすべてを1階で完結できる間取りにしておけば、将来的なリフォームの必要も減り、ずっと快適に暮らせます。
「常識」にとらわれない、シンプルな家づくり
「子ども部屋は2階」という固定観念。
でも、家族の暮らしを長い目で見れば、1階に子ども部屋を作る選択肢も十分に合理的で、むしろメリットが多い場合もあります。
こうした視点こそ、ムダのない、ストレスのない、将来も見据えた家づくりの第一歩。
まとめ:間取りは「未来基準」で考えよう
✓子どもが小さいうちは、親のそばが安心
✓思春期には少しの距離感も大切
✓巣立った後も無駄にならない“再利用できる部屋”に
✓老後の暮らしも視野に入れた動線計画を
私たちシンプルノートは、家族の未来まで見据えた「合理的な間取りと暮らしやすさ」を大切にしています。
間取りに正解はありません。
けれど、“将来の選択肢を広げておける家”は、きっとあなたの暮らしを豊かにしてくれるはずです。
オンライン相談会開催中!
「未来基準」で考える間取りってどんなもの?
オンラインでお気軽にご相談ください。
では、また。