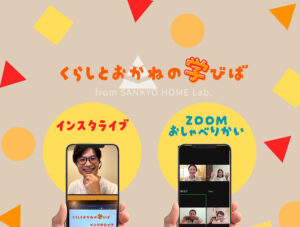深ければいいわけじゃない!今の暮らしに合った“使いやすい収納”の考え方
2025.10.31
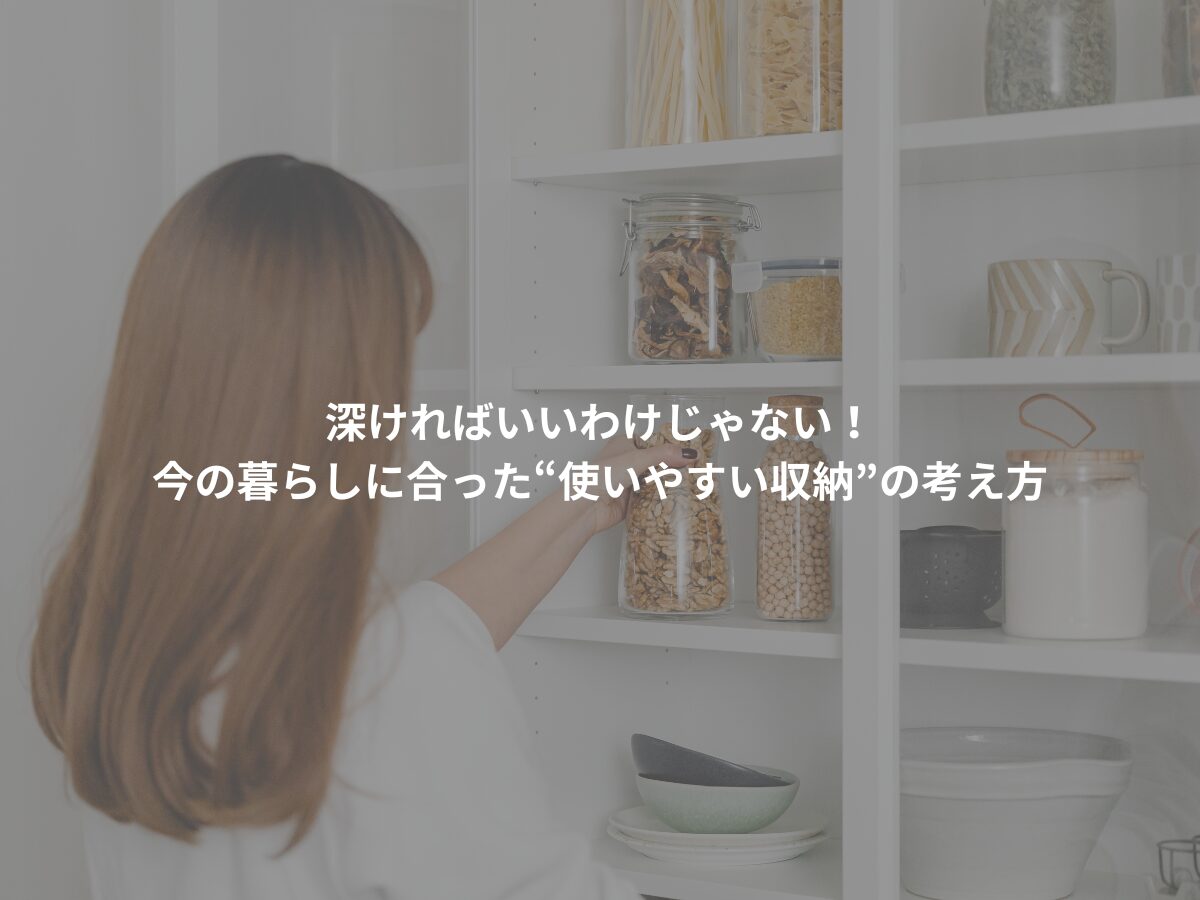
こんにちは。三協建設の堀内です。
時代とともに、暮らし方や家のあり方もどんどん変化しています。
その中でも、昔と比べて大きく変わったことのひとつが、あらゆるものの「薄型化」や「小型化」です。
CONTENTS
家電も家具も“薄く・小さく・軽く”なった時代
昔の家には、奥行きのあるブラウン管テレビや、大きなタンスがどんと構えていましたよね。
でも今は、テレビもパソコンもスリムになり、掃除機もコードレスでコンパクト。
場所を取らない家電が主流になっています。
さらに、クローゼット収納が一般的になったことで、昔は“嫁入り道具”と呼ばれたタンスを買う必要もなくなりました。
つまり、現代の家は「ものを置くために部屋を広くする」必要が少なくなったと言えます。
ではその分、家の中の収納はどうあるべきなのでしょうか?
実はこの「収納のつくり方」こそ、昔のままではもったいないのです。
奥行きのある“押入れ型収納”の落とし穴
いわゆる「押入れ」と呼ばれるタイプの収納。
奥行きが深く、2枚の棚板が標準仕様になっているものですね。
でもこの押入れ型収納、実際に使ってみると不便だと感じたことはありませんか?
奥のほうに収納ボックスを詰め込むと、手前のスペースが空いてしまう。
そしてそのスペースについ何かを置いてしまい、「奥のボックスに何を入れたか思い出せない…」なんてことに。
結果、どんどん“ブラックボックス化”してしまうのです。
空間をムダにしない「奥行き」と「棚板」の考え方
実は、押入れのような深い収納は、空間の余白が無駄になりやすいという欠点もあります。
収納ボックスの上が空いていても、そこにぴったり置けるものって意外とありません。
結局、上部がデッドスペースになることも多いんです。
収納を設計する際に大事なのは、「どんなモノを、どれくらい持っていて、どんな頻度で使うのか」。
これを考えた上で、収納の奥行きや棚板の枚数を決めることなんです。
リビングやキッチンこそ“浅い収納”がちょうどいい
細々したモノが多い場所――たとえばリビングやダイニング、キッチン。
このエリアに深い収納をつくると、どうしても奥の方にモノを詰め込んでしまい、取り出しにくくなります。
階段下収納だけが頼みの綱、というケースもよくありますが、その場合も奥行きが深すぎると、結局モノを探すのが大変に。
こうした生活空間の収納には、“奥行きが浅く、出し入れしやすい”収納を意識すると、日々のストレスがぐっと減ります。
棚板の数で収納力は何倍にも変わる!
収納をつくるとき、棚板の枚数は“なんとなく”で決めていませんか?
実は、棚板1枚の有無で使い勝手が劇的に変わるんです。
少ない棚板だと、どうしても空間にムダができてしまいます。
一方、しっかり棚を設けておけば、床面積を増やさなくても収納力を最大限に引き出せます。
棚板にはコストがかかりますが、それによって収納効率がアップし、家全体のムダが減ると考えれば、結果的にコスパのいい投資なんですよ。
現代の暮らしに合った収納設計とは?
ものが少なく、家電もコンパクトになった今。
家づくりで考えるべきは「どれだけ収納をつくるか」ではなく、“どんな使い方をする収納をつくるか”です。
・リビングには浅くて見やすい収納
・キッチンは動線に合わせてサッと取り出せる収納
・クローゼットは上から下まで無駄のない棚構成
こうした設計の工夫が、暮らしの快適さを何倍にもしてくれます。
まとめ
・現代の家電・家具は薄型化。収納スペースの考え方もアップデートが必要
・押入れ型の深い収納は使いづらく、空間をムダにしやすい
・奥行きの浅い収納と棚板の工夫で、使いやすく整理しやすい収納に
▽ 暮らしの工夫を学べる「くらしとおかねの学びば」へ
三協建設では、家づくりだけでなく、「暮らし方」や「お金の考え方」も一緒に学べる『くらしとおかねの学びば』を開催しています。
今回ご紹介したような収納づくりの考え方や、“間取りとお金のバランス”を整えるヒントもわかりやすく紹介。
これから家づくりを始める方にもぴったりの内容です。
では、また。